こんにちは、統一翻訳ライターの津山です。皆さんは、翻訳したコンテンツの著作権管理について正しく理解していますか?
昨今、ビジネスのグローバル化が発展し、自社のウェブサイトやマニュアルを翻訳したり、オンラインビジネス用コンテンツを、翻訳者や機械翻訳を通じて翻訳する機会も増えてきました。
ですが例えば、一度翻訳したコンテンツに手直しをすることは著作権上、問題はないのでしょうか?翻訳内容の著作権が一体誰に帰属するのか、実はよく知らない方も多いと思います。
著作権侵害による訴訟等のトラブルを防ぐためにも、自社の翻訳物の著作権が誰に帰属するのか知らなければならないのはもちろんのこと、すでに翻訳されている文書を引用する場合でも、誰にどのような許可を取れば良いのか、きちんと理解しておく必要があります。
そこで今回は、著作権の基本と翻訳に関わる著作権の帰属問題、そして翻訳を依頼するときに注意したいポイント3つを、翻訳会社の視点から簡単に説明します。
今後、コンテンツの翻訳を計画中の皆様は、この記事で翻訳に関する著作権の問題を理解し、訳文の取扱いに関する不安を解消しましょう。
翻訳前に知っておくべき著作権と著作権法とは
そもそも著作権とは?
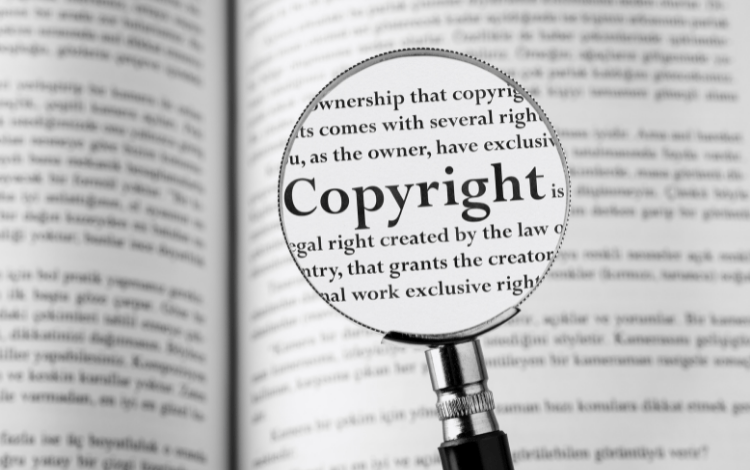
最初に、翻訳を依頼する場合には誰でも知っておくべき「著作権」と、著作権に関連するキーワードについて簡単に説明します。
公益社団法人著作権情報センターの説明によると、自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。
著作物とは、誰かが独自に創作したものであれば、小説、音楽、美術作品、建築物、写真、映画など全てが該当します。当然企業が作成したウェブサイト、キャッチコピーなども著作物にあたります。
著作物は、それが創作された時点で著作権が発生します。 著作権を得るための、公的な手続は必要ありません。
著作権法の中で、特に翻訳に大きく関わるのが「二次的著作物」という考え方です。二次的著作物はある著作物をもとに創作された著作物のことで、例えば企業があるコンテンツを翻訳会社に依頼して完成した翻訳物は「二次的著作物」に該当します。

著作権に関係する法律と注意点

著作権に関する法律「著作権法」の理解は非常に重要です。なぜなら翻訳会社によって創作された翻訳物は「二次的著作物」に該当し、翻訳物にも新しい著作権が発生するからです。
ここでは著作権法で定める権利のうち、翻訳に関係する部分を抜粋してご紹介します。
| 内容 | |
|---|---|
| 著作権の保護期間 | 著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後70年間(著作者が不明確な場合は公表後70年間) |
| 著作者人格権 | 作品を作った人の人格を保護する目的で定めた権利。公表権(著作者が著作物を公表するかどうか)、氏名表示権(著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか)などがある。 |
| 著作権(財産権) | 著作物の利用方法によって発生する権利を区分して定めたもの。翻訳権はこの財産権のうちの一つ。翻訳する場合は利用する前に著作権者の許可をもらうことが必要。 |
| 翻訳権・翻案権 | 著作権法27条に定められた著作物を翻訳、編曲、変形、翻案したりする権利のこと。 |
| 二次的著作物の利用権 | 著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利。 |
上記の条文から読み取れるように、著作権が発生している著作物は、創作した人(著作者)の了解なしに公表したり改定したりすることは許されません。この点は「二次的著作物」である翻訳文でも同様です。
つまり、二次的著作物があるコンテンツは、二人の権利者がいるということです。翻訳物をさらに別言語に翻訳する時などは、翻訳者と原作者、双方の許可が必須である点に注意なさってください。
翻訳したコンテンツの著作権は誰に帰属するのか

翻訳物は「二次的著作物」に該当するため、自社のウェブサイトを実際に翻訳会社や第三者の翻訳者に依頼した場合、翻訳物の著作権は、原則、翻訳会社や翻訳者に帰属します。
ただし翻訳会社が権利を放棄すると明言している場合や、委託契約で事前に二次利用権の帰属を規定している場合はこの限りではありません。
なぜ、訳文に著作権が発生するのか?と思われるかもしれませんが、質の高い翻訳を行うためには、訳文の使用地に合わせた翻訳(ローカライズ)や意訳が欠かせません。翻訳の良し悪しによって、小説、漫画、映画、ビジネス資料等、ありとあらゆるものの価値が変化します。
十人の翻訳者がいれば、十通り以上の訳文が存在します。原文が長ければ長いほど、多種多様な訳文が生まれます。一つとして同じ訳文は生まれません。翻訳者の知識や学問背景によって、彼ら独自の翻訳物(二次的著作物)が創られるのです。
なぜ翻訳にローカライズや意訳が必要なのかについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
一方で、翻訳会社を利用せず、自社で機械翻訳をした場合、二次的著作物の著作権は自社に帰属します。ただし、機械翻訳の場合は、不自然な翻訳や固有名詞の誤訳など、著作権問題とは別のトラブルが発生するリスクが高いことは、ご留意いただいた方がよろしいかと思います。
機械翻訳における誤訳例や問題点は以下のブログを参考になさってください。
翻訳物の著作権が大きな問題に発展した事例

翻訳物の著作権について正しく理解しておかないと、どのような問題が起こるのでしょうか?ここで過去の実例を一つご紹介します。
平成13年に『絶対音感』という書籍に引用された文章が、翻訳者に無断で複製され、かつ翻訳者の名前を開示しなかったとして裁判になった事件がありました。判決では著者と出版社に多額の賠償金の支払いが課されました。
このように、二次的著作物の著作権について把握しておかないと、思わぬ事態が起こるリスクがあります。そのため、翻訳したコンテンツを改定したり二次利用したりする場合は、十分に著作権に配慮する必要があります。
またその他にも、二次的著作権は原作者の著作権が切れた後も翻訳者に残り続けるケースがあることや、著作権を譲渡する時は翻訳者が持つ二次的著作物の権利関係も整理する必要があることなどに注意が必要です。
著作権トラブルを回避するための翻訳依頼時のポイント2つ
最後にこれから翻訳会社に翻訳を依頼する方へ、翻訳物の著作権をめぐるトラブル回避のために大切なポイントを、翻訳会社の目線から2点お伝えします。
翻訳物の著作権の帰属先を契約書に明記する
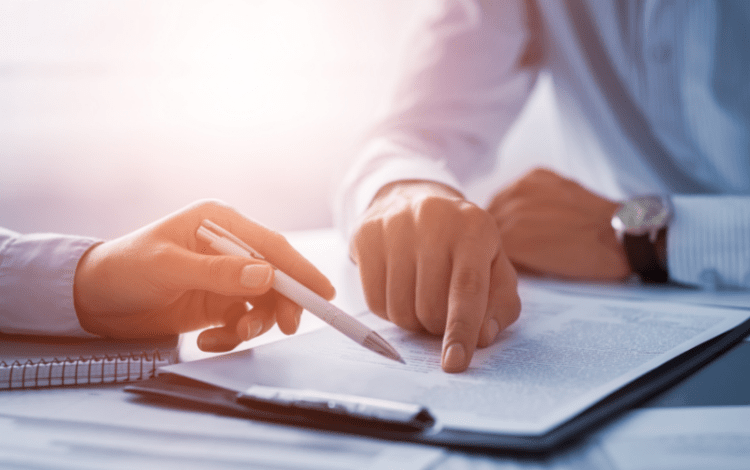
翻訳を依頼する時は、翻訳されたコンテンツの著作権の扱いについて事前に確認し、帰属先について契約書に明記しておくことが重要です。
翻訳会社の中には、統一翻訳のように翻訳物の著作権を放棄を最初から宣言している会社もあれば、著作権は放棄しないと明言している会社もあります。どちらにせよ、契約の時点で契約書に帰属をきちんと明記することで不要なトラブルを回避できます。
著作権・二次使用権に関する取扱い方や、翻訳物の重要性や目的、今後の翻訳物の二次利用の有無などを総合的に判断した上で、翻訳会社を選定してください。
二次的著作物に該当する範囲を契約書に明記する
ご利用予定の翻訳会社が、翻訳物(二次的著作物)の著作権を放棄していない場合は、二次的著作物の範囲や使用許諾のルールを、契約書で明記することが重要です。
例えば、翻訳会社がデザイン調整まで行う場合はそのデザインも二次的著作物に含まれるのか?翻訳物の軽微なアレンジや文言修正は可能か?第三者への使用許諾は下りるか?など、ケース・バイ・ケースで、条文を追記しておくと、想定外のトラブルが起こるリスクを防ぐことができます。
委託契約書に記載する内容を決める際に、自社内で将来にわたり翻訳物がどのように利用されるかを、洗いざらい列挙することも重要です。翻訳物の利用目的を整理して、将来起こりうるケースを契約書内で明文化しておくことをお勧めいたします。
もし、海外の企業と著作権に関してやりとりが発生する場合は、契約書や使用許諾書など、法務関連書類の翻訳も欠かせません。これらの法務関連書類の翻訳に関する注意点は、以下の記事をご参考になさってください。
関連記事:法務翻訳を専門家に頼むべき理由とは?プロが実例を交えて紹介
重要な翻訳は著作権管理の心配が不要な統一翻訳へ

著作権のリスクを回避し、安心して翻訳物を利用するためには、統一翻訳の利用がオススメです。統一翻訳は50年以上の実績を持つアジア最大の翻訳会社で、契約書には、翻訳物の著作権は「全てお客様に帰属する」ことを明記しています。譲渡対価も請求しません。
統一翻訳は世界中に11,000人以上の翻訳者がおり、業界に精通した最適な翻訳者を見つけることが可能です。また質の高い翻訳には欠かせないネイティブチェックにも対応しています。
更に品質面でも、ISO17100やISO9001といった国際翻訳規格にも勝る、TDQCMP®標準作業体制を構築しており、台湾のTSMCや日本のトヨタなど、世界を代表する企業様からも選ばれる、信頼と品質への評価が高い翻訳会社です。
現在、統一翻訳では300字の無料トライアルを実施しています。もし著作権の心配もなく、ストレスフリーで、翻訳物を自由に利用したいとお考えのお客様は、ぜひこちらから統一翻訳へお問い合わせください。

